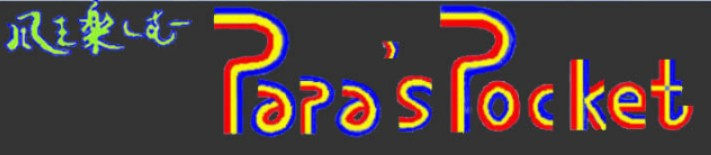|
34『古事記』では豊玉毘売・豊玉毘売命、『日本書紀』では豊玉姫と表記される。 海神(わたつみ)の娘で、竜宮に住むとされる。 真の姿は八尋の大和邇(やひろのおおわに)であり、異類婚姻譚の典型として知られる。 神武天皇(初代天皇)の父の鸕鶿草葺不合尊の母であり、天皇の母の玉依姫の姉にあたる |
 |
35大物主神(おおものぬしのかみ、大物主大神)は、日本神話に
『古事記』では坐御諸山上神(みもろのやまのうえにますかみ)、美和之大物主神(みわのおおものぬしのかみ)、意富美和之大神(おおみわのおおかみ)とも記す。
『日本書紀』では大三輪之神、大三輪神とも記し、大己貴神の幸魂奇魂とする。
『播磨国風土記』では八戸挂須御諸命(やとかけすみもろのみこと)、大物主葦原志許(おおものぬしあしはらのしこ)とも表記する。
『出雲国造神賀詞』では倭大物主櫛𤭖玉命と記す。 |
 |
36天菩比神(あめのほひのかみ)
『古事記』では天之菩卑能命、天菩比命、天菩比神、『日本書紀』では天穂日命と表記される。天照大御神と須佐之男命が誓約をしたときに生まれた五男三女神の一柱。天照大御神の右のみずらに巻いた勾玉から成った。物実(ものざね:物事のタネとなるもの)の持ち主である天照大御神の第二子とされ、天忍穂耳命の弟神にあたる。葦原中国平定のために出雲の大国主神の元に遣わされたが、大国主神を説得するうちに心服して地上に住み着き、3年間高天原に戻らなかった。後に他の使者達が大国主神の子である事代主神や建御名方神を平定し、地上の支配に成功すると、大国主神に仕えるよう命令され、子の建比良鳥命は出雲国造及び土師氏らの祖神となったとされる。また、出雲にイザナミを祭る神魂神社(島根県松江市)を建てたとも伝わる[2]。 |
 |
37天之菩卑(アメノホヒ)
天照大御神と須佐之男命が誓約をしたときに生まれた五男三女神の一柱。天照大御神の右のみずらに巻いた勾玉から成った。物実(ものざね:物事のタネとなるもの)の持ち主である天照大御神の第二子とされ、天忍穂耳命の弟神にあたる。葦原中国平定のために出雲の大国主神の元に遣わされたが、大国主神を説得するうちに心服して地上に住み着き、3年間高天原に戻らなかった。
|
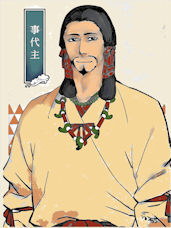 |
38武松(ぶしょう)は、中国の小説で四大奇書の一つである『水滸伝』(金瓶梅)の登場人物。梁山泊108人の豪傑の1人。人喰い虎退治、潘金蓮と西門慶の仇討ちなどで知られる。
天傷星の生まれ変わりで、序列は梁山泊第十四位の好漢。渾名は行者(ぎょうじゃ)で、修行者の姿をしていることに由来。
鋭い目と太い眉をもつ精悍な大男で、無類の酒好き。拳法の使い手であり、行者姿になってからは2本の戒刀も用いた。
|
 |
39建御雷之男神(たけみかづちのをのかみ)
天津神。高天原の「武」の象徴。神話「出雲の国譲り」では、出雲の統治権を譲渡させる功績を挙げ、「神武東征」においては神剣を遣わし神武天皇を救います。鹿島神社総本山の鹿島神宮の祭神「鹿島神・鹿島さま」でも知られる。日本三大軍神の一柱であり、建御名方神と共に相撲の祖神とされます。 |
 |
40玉祖命(たまのおやのみこと)は、 日本神話 に登場する神である。玉造部(たまつくりべ)の祖神とされる。 『 古事記 』にのみ登場し、『 日本書紀 』にはこの名前の神は登場しないが、同神と見られる神が登場する。 別名に 玉屋命 (たまのやのみこと)、 櫛明玉命 (くしあかるたまのみこと)、天明玉命(あめのあかるたまのみこと。岩戸隠れの際に八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)を作った。天孫降臨の際邇邇芸命(ににぎ)に附き従って天降るよう命じられ、天児屋命(あめのこやね)、布刀玉命(ふとだま)、天宇受売命(あめのうずめ)、伊斯許理度売命(いしこりどめ)と共に五伴緒の一人として随伴した。絵はその一部を切り出したもので実際この神様が玉祖命かどうかは実際のところ不明。
|
 |
41火が盛りのときに産まれたのが火照命、次が火須勢理命、最後に産まれたのが火遠理命だ。三男の火遠理命は、別名天津日高日子穂穂手見命(あまつひこひこほほでみのみこと)といい、天皇家の祖先にあたる。
日子穂穂手見(ヒコホホデミ)は日本神話の物語の中では有名な話とされている「海幸彦山幸彦」の主人公で、高天原から地上に降り立ったニニギの三人の子供の末っ子にあたり、稲穂の神として知られています。
また、名前の中の「穂」の字を「火」としている事もあり、ヒコホホデミは幼名を「ホオリ」と言いますが、この名は炎が衰えている様をあらわし、意味としては稲穂が実っている頭を垂れている様を象徴しているとされています。
|
 |
42天稚彦(アメノワカヒコ)下照姫との恋に溺れて使命を放棄し、その罪によって亡くなるという悲劇的かつ反逆的な神として、民間では人気があった。
天若日子と阿遅鉏高日子根神がそっくりだったということで、本来同一の神であったとする説もある。すなわち、アメノワカヒコの死とアヂスキタカヒコネとしての復活であり、これは穀物が秋に枯れて春に再生する、または太陽が冬に力が弱まり春に復活する様子を表したものであるとする。されている。 |
 |
43塩椎神(しおつちのかみ)
シオツチノオジ神は宮城県の塩竈神社の祭神です。 ここを本拠地としてその分霊を祀る神社が全国に広がっています。 海の神、潮の神とされ、塩土老翁神を祀る著名な神社としては、宮城県塩竈市の鹽竈神社が挙げられる。現在の鹽竈神社では、3座の祭神のうち別宮(べつぐう)の祭神として塩土老翁神が祀られている。
|
| |
|
| |
|